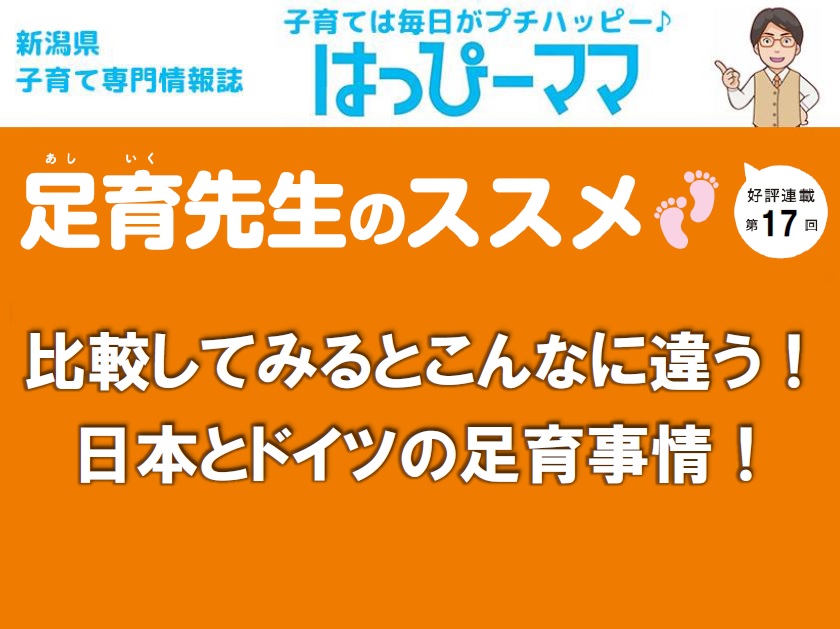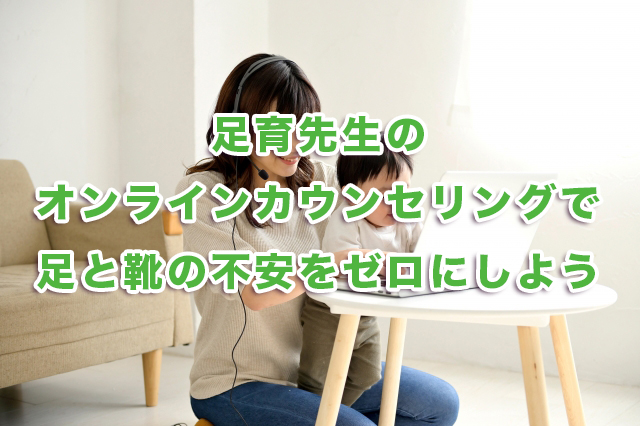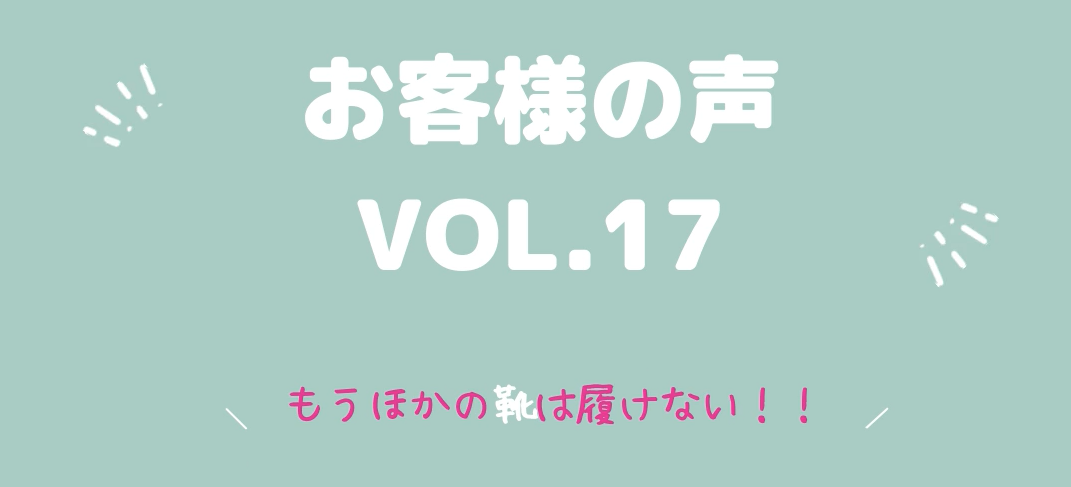目次
子ども用専門情報マガジン「はっぴーママ」 新潟版から「足育先生のススメ」をお届けいたします
「子ども用専門情報マガジン「はっぴーママ」 新潟版」は、子育てに役立つ生活情報・地域情報を満載し、新潟のママが元気でハッピー になるためのライフスタイルを提案しているフリーマガジンです。県内私立幼稚園・保育園、小児科、産婦人科、耳鼻科などの提携医院・総合病院、子育て支援施設、ショッピングセンター、ドラッグストア、銀行、図書館等で偶数月25日(隔月発行)に配布しています。
「足育(あしいく)」の大切さをお父さん、お母さんを始め子どもたちにお伝えしたく、足育先生®が毎号連載をしています。
今日は、「足育先生のススメ」第17回から内容を抜粋・編集してお届けいたします。
この他の過去バックナンバーは画像でもご覧いただけます。https://ashiiku.net/2021/08/01/happymama45/
足育とは?
食育という言葉は広く定着してきましたが「足育」という言葉があることを、みなさんご存知ですか?
足は全身を支える土台であり、身体全体の健康に大きな影響を
与えています。足育とは、足、足の指・爪、さらに靴の選び方・
履き方を含め正しい知識を得て、理想的な足を育てることをいいます。
人生80 年の中で一番大切な時期が3 ~ 7 歳です。
この時期に足育できた子どもたちが将来活躍できるといえます。
比較してみるとこんなに違う! 日本とドイツの足育事情!
 ドイツは靴文化が1000年以上あるのに対して、日本に靴を履く文化入ってきたのは戦後70年ほどしかありません。
ドイツは靴文化が1000年以上あるのに対して、日本に靴を履く文化入ってきたのは戦後70年ほどしかありません。
ドイツは国をあげての足育文化があるので、5歳までに9回の健診があり、足から診断され病院とマイスター(日本でいう靴が作れるシューフィッター・ドイツの国家資格)が連携して靴やインソールを作成して変形のない足を国がサポートしてつくっていきます。
日本とドイツの足育比較
| 日本 | ドイツ | |
| 靴文化 | ●ゲタの文化(靴文化70年程)
※戦後靴の普及はあったが、靴に対する知識(履き方・選び方)が無かった為ゲタ文化の名残が今でもある。 |
●靴の文化1000年以上
※足と靴の知識は国から、または親から子どもに厳しく伝えられる。 |
| 購入方法 | ●子どもが主導権を持つ
●計測しないで靴を選ぶ ●子どもが選ぶキャラクターやスッと履ける履き口の広い靴を選ぶ |
●必ず親が選ぶ
●子どもが自ら店員に声を掛け計測する。 ●1人の子どもに1時間かけって靴を選ぶ。 ●マジックやひも靴を選ぶ(キャラクターはある) |
| 靴教育 | ●靴教育制度がない(国の関心が低い)
※指定靴問題。人は顔が違うように足も違うが、規則だからと合わない靴を履かせる |
●靴教育は赤ちゃんの頃から国や親から学び、靴教育しながら靴選び
●小学校1年生でひも靴がはけるように幼稚園でひも結び練習を絵本でする |
| 靴メーカー | ●靴メーカーすべてがサイズ規格がバラバラ
●同じサイズでもずいぶん大きさが違う ●親が困惑し子どもに選ばせる |
●ほとんどの靴メーカーが安心と信頼のWMS協会に所属してサイズ規格を整えているので、迷わず靴選びができる
●赤ちゃんが舐めても安全な薬剤を使用する
|
| 良い靴の基準 | ●幅が広い・軽い・手を使わずに履ける
※かかとを踏んだり、つま先トントン、手を使わないで履くなど間違った認識をしている。 |
●ひもかマジックテープで足を固定する
●足なじみのよい革靴を履かせる ●幅は3種類(大・中・小)から選ぶ ●頑丈な少し重い靴を選ぶ |
日本とドイツの足と靴の文化の違いを見ていかがでしたか?
 日本の靴 歩行履き口がゆるく、良く締めても足にフィットしません。耐久性も低く軽いために時間が経つと靴が変形し、子どもの運動量に耐えられなくなり、底が傾き、足も傾いてしまいます。
日本の靴 歩行履き口がゆるく、良く締めても足にフィットしません。耐久性も低く軽いために時間が経つと靴が変形し、子どもの運動量に耐えられなくなり、底が傾き、足も傾いてしまいます。
 ドイツ(ヨーロッパの靴)
ドイツ(ヨーロッパの靴)
履き口が狭く足首にフィットします。
頑丈に作られていますので、柔らかい軟骨の子どもの足をしっかりと守ります。
ドイツではファーストシューズから頑丈な靴を正しい履き方と選び方で履かせるために足指の変形や扁平足やO脚・X脚で悩む子どもは本当に少ないのです。
足育ポイント 最初にゆるいフィット感で履くことをから体が覚えてしまうと、ルーズな感覚が基準となります。
足育先生の想い…私の想いは、日本に足と靴文化を根付かせることで、子どもの将来と才能を発見していきたいと思っています。
その為には「親(大人)」が足と靴の正しい知識を持ち、子どもに伝えていくこと。それが引き継がれ、日本に正しい靴文化ができていくことです。
足育活動は日本の明るい未来づくりのために重要な活動です。
ぜひご協力お願いいたします!
足育の全てはここにあり!? 足育先生Ⓡの情報はこちらから
足育を日本中に広めるために足育先生Ⓡは講演会やSNSで啓蒙しています。まだまだ足育を知らない親御さんは沢山います。是非子ども達の一生の足を守る為にも沢山のシェアといいねのご協力をお願いします。
いつか日本の文化に足育が広がり、親から子に足育を当たり前に伝える文化になる事を願っています。
【足育オンラインカウンセリング情報】!
足育先生Ⓡの「足育オンラインカウンセリング」が全国どこでも受けることができます!
【やり方についてはこちらから】
【ぜひ受けて欲しいお悩みについてはこちらから】
【オンラインカウンセリングを受けていただいた方のご感想はこちらから】