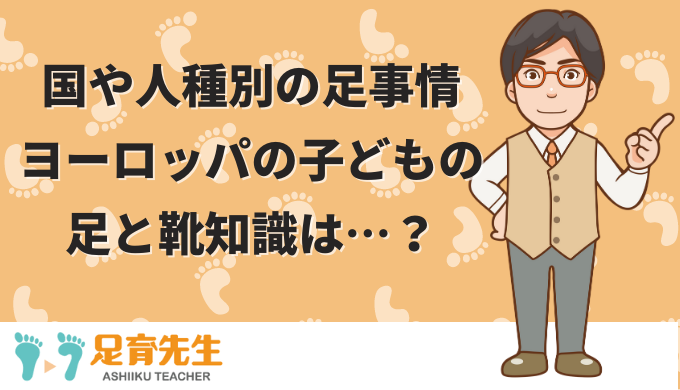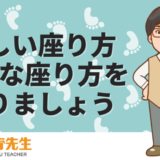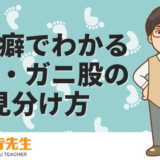足育先生が何度もドイツに足育調査に行くということからもわかるとおり、ドイツは足育先進国。
ドイツではファーストシューズに紐靴を締める、しっかりしたものを選び、正しい靴の履き方は親が教え、歩行量も幼稚園・保育園の頃からとても重要視しています。
このような話を聞くと、ヨーロッパすべての国が足育先進国で、日本はまだまだなのかと思ってしまいがちですが、実はそうでもありません。
ヨーロッパに限らず、世界各国、それぞれの文化や環境、骨格の違いによる足トラブルの違いなどもあります。
今回は『ヨーロッパ=足育先進国』という認識の間違いと、国や人種による足トラブルの話を、足と靴の専門家がお伝えしていきたいと思います。
目次
何度も、この足育先生の記事で紹介したように、ドイツでは、子どもの足の育成に関して、国を挙げて熱心に教育しています。

写真の右が日本の子どもが履く靴。
そして左の靴はドイツで一般的な幼児の靴ですが、履き口の広さがここまで違うことに多くの方が驚かれます。
また、ドイツの場合、子どもであっても2歳くらいのうちに靴を紐で締めるということを学ばせます。。
世界のあるある話になってしまいますが、アメリカでは歯並びが悪いと親の教育が悪いと笑われてしまいます。
日本では箸の持ち方などで、親の教育・しつけをみる傾向がありますが、ドイツでは靴をしっかり締めて歩く事ができないと、親のしつけが悪いと笑われてしまうほど、足育に熱心なのです。
さらに、ドイツでは靴選びに1時間時間をかけて、足の長さはもちろん、横幅もしっかりと測定して、ぴったりの靴を選ぶようにしています。
その甲斐あって、ドイツでは理想的な靴を履いて、理想的な歩き方をするなどで足育を上手に行い、理想的な筋肉の付き方、良い姿勢を大抵の人たちが得ることができているのです。
これは、靴文化が長いこと(日本の靴の歴史は約60年、ヨーロッパは約500~600年)で靴に対する認識が、しっかりしているという理由からなのですが、一方で同じヨーロッパでも足育を知らない国もあるのです。
ドイツの靴や足に対する教育の話を聞くと、ヨーロッパ全体が足育に熱心なのかと思ってしまいますが、実はそうでもありません。
足育先生が行ったベルギーでは、足育が知られておらず、逆に先生が質問攻めにあったということもありました。

ベルギーは育先進国なのに……とちょっと驚きますよね?
世界には靴文化ではない国もたくさんまだあり、また、ヨーロッパもたくさんの国があります。
それぞれに異なる文化や歴史があり、また環境や風土が違うため靴に対する認識も異なっているのです。
ですので、一概にヨーロッパだから足育先進国。
アジア圏だからよい靴文化がない……という考えはちょっと間違っており、教育の見本はベルギーを、足育の見本はドイツをと、各国の良い部分を参考にしていくことが、日本がより良い国になっていくヒントなのではないかなと思っています。

このように、近くの国でも文化や風土、歴史なんかで足育に対する認識が異なるように、人種による骨格の違いも足トラブルの違いに繋がったりしています。
例えば、日本人に多い扁平足や浮指などは、素足や草履や下駄で長時間歩く事の多かった昔にはあまり起こらない症状でした。
ですが、靴を履くことが当たり前になり、車や座り仕事ばかりで歩く事の減った現代日本人は、その骨格ならではの浮指などの問題が起こるようになりました。
なぜなら、日本人は元々靴文化はなく、下駄や草履という「足指の間に紐を挟んで歩く」という文化が根付いた人種のため、21世紀の現代でも、靴の紐やマジックを締めて靴を履くということが軽く見られがち。
また、日本人は元々着物を着て刀を持っていた人種でした。
刀はなで肩で猫背でなければ使いにくい武器なのですが、そもそも猫背ということは、骨盤が後傾しているということ。
武士に限らず、昔の田植えの浮世絵などを見てみると、しゃがんで田植えしているお日百姓さんが描かれていたり、薪を背中に背負っている絵があったりすることから、日本人は総じて骨盤が後傾する傾向にある人種だと言えるでしょう。
つまり、日本人は元々骨盤が後継しやすく、内股、また、すり足をよしとする感覚も残っているため、足の指を使ってかかとを上げて歩くという意識が少し薄いということがわかりますね。
それに輪をかけて、現代人は座ることが多く、さらに日本人は骨盤が後傾しやすく、後ろ体重になりやすくなってしまったのです。
そのため重心が後ろ(かかと)にいきやすいということもあり、浮指が多いのではといわれているのです。

一方、欧米人はサーベルやフェンシングで戦い、コルセット付きのドレスを着ていた文化を過ごしてきました。
サーベルなどは背筋がピンと反っているくらい伸びていないと構えにくいし、腰が反っていないとコルセットを着用することができません。
つまり、欧米人は元々反り腰で、骨盤が前傾している傾向にあるということなのです。
そういえば、欧米人に限らず、アフリカの女性が腰が物を運ぶときに、ターバンを巻いた頭の上に大きなツボを乗せて歩く動画なんかよく見ますが、あれは腰が曲がりにくいから。
欧米人の場合骨格の関係上、骨盤が前傾してしまうことが多く、また、昔からハイヒールの文化があったため、かかとよりもつま先側に力が入りやすい傾向にあります。

マリーアントワネットやエリザベス女王の肖像画などを見てもらうと、昔からハイヒールを履いていることがわかりますよね
そのため、浮指とは逆に『ハンマートウ』と呼ばれる、足指がギュっと角に曲がって、まるで猫のカギ爪のようになってしまっている状態のことが多いのです。
浮き指と真逆の『ハンマートウ』という足トラブル……。
これだけでも骨格の違い、歴史や文化の違いで足トラブルの種類が異なるというのがよくわかって、面白いですね!

このように、骨格の違いや文化の違いで足トラブルも様々なものになる、ということがわかったかもしれませんが、では、多くのスプリンター生んでいる、アフリカなどではどうなのかというと……。
気温が暖かで、砂地が多い等、元々裸足で歩く事も多いアフリカなどの国では、足もしっかりしており、さらには黒人は腸腰筋などが発達しており、骨格的にも瞬発力に適した身体付をしているため足トラブルは少ない傾向があります。
ですが……。
アフリカでは砂ノミと言って、足の裏に卵を産み付ける、背筋がゾワゾワするようなノミに寄生される事案が多く、靴下や靴を履くことを勧められる場合もあります!!
他にもサンダル文化の東南アジアでは、湿地のを裸足で歩くことで寄生される事の多い、住血吸虫症という寄生虫がいたりするので、「裸足で歩ければ全てOK」ということでもありません。
足や靴一つ取ってみても、各国、各人種、それぞれの文化背景や歴史などの違いがよくわかり、世界の広さを常々と思い知らされますね。
特に骨格に関しては生まれ持っての遺伝子の問題。
肌の色や目や髪の色が人種によって違うのと同じ問題ですので、仕方のないことなのですが、そうした骨盤が前傾している文化の履物を、骨盤が後傾している文化の日本人が使うのであれば、それなりに、長く靴を履いている文化から多くを学んだ方が早いのですが、遺伝的骨格という根本的な違いがある以上、日本人向けの足育が必要となってきますよね。
我々足の専門家は、日本人の環境・骨格に合った足育について、これからも発信していきたいと思っています。
ぜひ、当ブログサイトやInstagramなどを登録し、足育について最新の情報を入手できるようにしていってください!!
子どもの成長・発達には、土台となる『足』の正しい成長『足育』が欠かせません。
ぐずり・もたつき・姿勢不良等など。
靴と足のチェックで子育ての悩みも解決できることも。
・講演実績年間50回
・相談件数年間2000件
靴と足の専門家、足育先生に無料で相談できる「LINE相談」はこちら!!

足と靴の相性もアドバイスいたします。