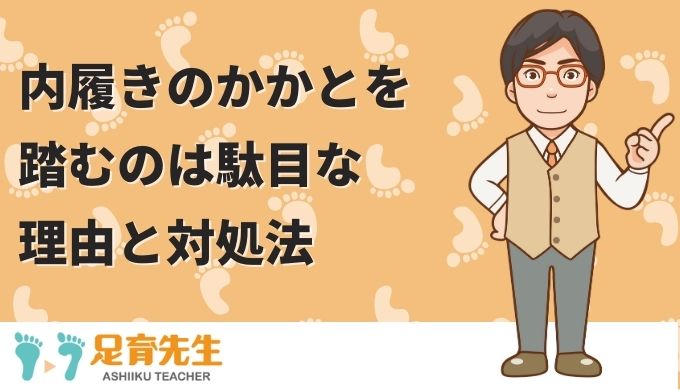現在、日本の学校のほとんどが、校内では「上履き(内履き)」を履かせるようにしています。
それは衛生的にすごく良いことなのですが、足育の観点からいうと、この上履き文化はあまり良くないもの。
いいえ、屋内に入るときに外靴を脱ぐということは良いのですが、足の形は千差万別、ましてや成長期の子どもたちに画一的な形の、もろく薄い靴を履かせていくということが足育としては賛同できない部分。
さらには、上履きは柔らかいのでかかとを踏みやすく、それによってさらに良くない影響が現れてしまうのです。
目次

上履きに限らず、靴のかかとを踏んで歩いたことは、恐らく大人になるまでに1~2回は絶対にあるのではないでしょうか。
特に、学生時代などは『かかとを踏んで歩く姿がかっこいい』と思っている子もいたりしましたよね。
確かに、漫画やアニメ、ドラマなどで、オラオラ系(笑)のキャラクターを思い出してみると、靴のかかとを踏んで、すり足・がに股で歩いていることが多かったはずですし、今もヤンキーなどが描写される際には大抵かかとを踏んでいるキャラが描かれているでしょう。
若い子どもたちにとっては、マナーとして良くないことと分かっていても、その姿にちょっと憧れをもってしまうのでしょう。
日本にはそういった風潮が昔から根強く残っているのか、実は、この靴のかかとを踏む行為は日本独特の習慣とも言えるのです。
『靴で人を見る』『靴はその人の人格を表す』ということわざがヨーロッパにあったり、特に『靴は足を守るもの』という考えのドイツではかかとを踏んで歩くという行為は、あり得ないほどのこと。
それはなぜかと言うと、かかとは靴の命と考えられているから。
人間は歩行の際、かかとから降りて足指で地面を蹴ります。
かかかとから降りたとき、最初のインパクトの際に固定性があれば、足は揺れずに前へ蹴り出すことができます。
実際、靴のかかとを触ってみると分かるのですが、良い作りの靴は、かかとが踏んで歩けないよう、指で押したくらいではビクともしないくらい靴のカウンター部分が固くできています。
かかとにしっかりと強いカウンターが入っている靴であれば、歩いている時に上にのっている足の筋肉が無駄に揺れることがないので疲れにくく、歩行が正常になるのです。
しかし、靴のかかとを踏んで真っ平らにして、かかとに固定性を無くしてしまった場合はどうでしょうか?
簡単に言うと、もはやそれは『スリッパ』ではないでしょうか。
これでは、“かかとから降りる”ということができなくなってしまいます。

しかも、かかとを踏んだ靴の場合、スリッパよりももっと足に良くない履き物になってしまいます。
それは、踏んだかかとの布の凸凹で、かかとがより不安定になるからです。
すり足で歩いたとしても、少なからず、かかとから着地します。
その時に、踏んだためにできてしまったかかとの凸凹により、スリッパよりもさらにかかとがぐらつくので、身体に力を入れていないと歩けなくなってしまうのです。
このかかとのぐらつきが大きくなればなるほど、その分身体に力が入り、足も身体も緊張状態が続くようになります。
つまり、かかとを踏んだ靴は『スリッパよりも不安定な靴』という悲しい履き物に成り下がってしまうのです……。

上履きの場合も、その他の靴の場合も、一番支えなくてはならない『かかとの芯』を踏む行為は“足を守る”という靴の役割が無くなってしまうので、絶対にNGです!
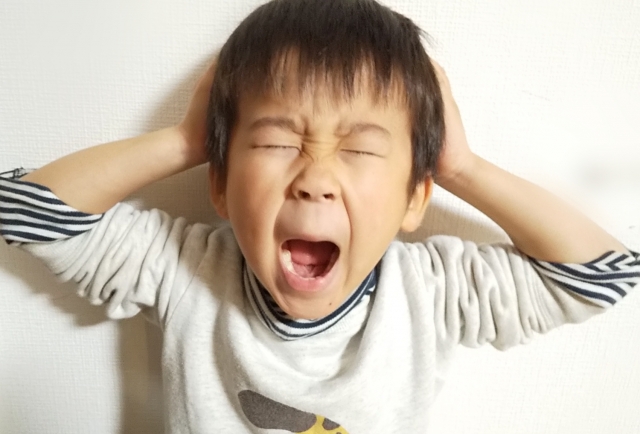
上履きのメリットとしては、外の汚れを持ってこない・安価で経済格差を知られることがない・洗いやすい、などがあげられますが、履き口が広く柔らかいので、子どもの足をしっかりと支えられない・全て同じ幅で作られているので、各々の子どもの足の形に合ったものを選べない、など足育の観点からするとデメリットが多い靴。
それに加え、かかとを踏んでしまった場合、『すり足』と呼ばれる歩き方になってしまいます。
すり足とは、恐らく読んですぐわかると思いますが、足が上がらない状態で歩くこと。
この状態で歩くと、足の筋力の低下により、身体がとても疲れやすくなってしまうのです。
その他、こうした歩き方から猫背になる・肩こりになるなどの弊害が起こることもあります。
そうした弊害が起こると、例えば肩こりが原因で、脳へ送られる酸素血流量が低下し、それに伴い集中力の低下も起こりうる……と、良くない事に繋がっていくのです。
そして、かかとを踏まれることでスリッパよりも不安定な靴になってしまった上履きを履くことで、歩く度に、かかとのぐらつきが大きくなります。
それをなんとか止めようとグーっと足に力が入り、身体は常に緊張状態が続くことに。
これが一日中続くと、イライラして、一日の終わりには相当な疲れを感じ、ストレスがたまった状態に……。
この、ストレスがたまった状態、実は人が怒っているときの足の状態と同じなのです。
何があったわけでもないのにイライラしがちだったり、急にキレる……なんてことが続いた場合、もしかすると、かかとを踏んで過ごしていることが原因かもしれません。
そういえば、ヤンキーなどはすぐにキレたりすますよね(苦笑)

上履きのかかとを踏む行為は、足と身体に悪影響でしかないことが分かっていただけたでしょうか。
近年、日本の教育現場でも、靴本来の役割や足育の重要性が認知され始め、マナーとしてだけでなく、靴のためにも、子どもたちの身体のためにも、『上履きや靴のかかとを踏まない・踏ませない』という指導がされています。
教育現場では踏み癖のチェックをし、その理由をヒアリングするするようにしている場所も増えています。
ちなみに、かかとを踏む理由で最も多いのは「上履きが小さいから」。
「かっこいいから」「きちんと履くことが面倒だから」ならば、子どもに対して踏まないよう促していけばいいのですが、サイズアウトは親御さんの問題でもあります。
子どもはただ、足の指を維持したいと思って、かかとを踏んでしまっているのです。
毎週末、子どもが上履きを園や学校から持ち帰ったら、まず踏み癖がないかチェックしましょう。
そして、踏んでいる場合は「なぜ踏んでいるのか」話を聞くことも大切です。
サイズアウトの場合は購入が必要ですし、上履きは幅が選べないので、足に痛いところがある場合は、何らかの対処をしないと足の変形につながってしまいます。
もし痛みの理由がわからないなど、親御さんでは解決できない場合は、私たち靴と足のプロにご相談ください。
また、靴を履く際に、急かさないことも大切です。

「早く履いて!」はNGワード。
子どもは急かされると、とにかく玄関から出ようと『取りあえず』かかとを踏んで出てしまいます。
学校の場合でも、たくさんの生徒が下駄箱に集まっていたら、急いでしまって上履きのかかとを踏んでしまうでしょう。
でも、この“とりあえず”で靴の命は終わってしまいます。
早くしてほしい気持ちはぐっと堪え、「かかとトントンギュー」を合い言葉に、正しい履き方を習慣づけましょう。
ちなみに、足育先生監修の園では、園の先生方がとても熱心に足育に取り組んでいるため、靴のかかとを踏むといことはもちろんありませんし、正しい靴の履き方が身についているので、子どもたちの足はとても良い成長をしています。
こういった足育に興味・関心をもった園や学校をもっと増やし、日本での靴に対する認識を変えていきたいと私たちは強く願っています。
最近では、徐々に足育への関心が高まり、『かかと踏み防止の上履き』が販売されるようになりました。
参考:朝日新聞 かかと踏みにくい上履きヒット 樹脂の出っ張りつけ開発
その工夫とは、上履きのかかと部分に樹脂の出っ張りがついていて、かかとを踏んだとき、この出っ張りがグッとかかとに食い込み、かかとを踏まないよう予防するという靴。
カウンター部分は簡単に倒れてしまいますが、踏み癖がつかなくなるという点では、とてもいいアイデアですね。
かかとを踏んでしまう癖のあるお子さんの場合、学校指定の上履きがある場合は難しいですが、色だけ指定されている場合などは、こちらの上履きを履かせてみるのも良いのではないでしょうか?
家庭でも学校でも、かかとを踏んで過ごすことがないよう、私たち大人が気をつけてあげるようにしましょう。
子どもの成長・発達には、土台となる『足』の正しい成長『足育』が欠かせません。
ぐずり・もたつき・姿勢不良等など。
靴と足のチェックで子育ての悩みも解決できることも。
・講演実績年間50回
・相談件数年間2000件
靴と足の専門家、足育先生に無料で相談できる「LINE相談」はこちら!!

足と靴の相性もアドバイスいたします。